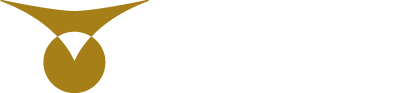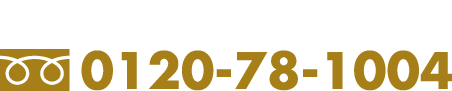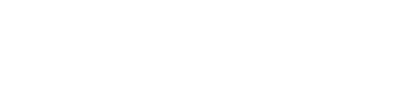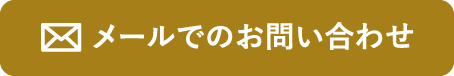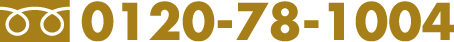#料金の目安について
自費出版の費用について
自費出版の費用は、原稿分量や判型、カラーの有無、製本仕様、初版部数、流通方法によって変動します。東洋出版では、自費出版の目的に合わせて仕様を設計し、自費出版の費用内訳を明確にしたお見積もりをご提示します。はじめての自費出版でも比較検討しやすいよう、項目ごとに根拠を示し、納得感のある自費出版の費用設計を行います。
料金表
本の名称について
本の様式は多々ありますが、ここでは分かりやすいように最も基本的な体裁を説明しています。

本文(ほんぶん)
まさに本の中身をいいます。
表紙(ひょうし)
書籍本体の一番外側の部分です。
カバー
表紙の上にかけられている紙。本来の目的は表紙の傷みや汚れの防止ですが、本の「顔」としての役割も大きく、様々なデザインや素材が施されます。
帯(おび)
お客様に本の魅力をアピールし、手にとってもらうことを目的に、内容説明やキャッチコピー、推薦文などを印刷している、カバーの上に巻く細い紙です。
見返し(みかえし)
表紙と本の中身を接着するために用いられる紙で、表紙や本文を印刷する紙とは異なる用紙が選ばれるのが一般的です。
本扉(ほんとびら)
本の「中身」の最初のページです。書名と著者名などを印刷します。
本文を印刷する紙とは異なる紙を用いたり、カバーのデザインに呼応したデザインを施したりすることもあります。
本の大きさ(判型)について
下記は一般的な本の大きさです。上製の場合は表紙が本文より大きくなりますので、本のサイズは縦横ともに
下記の数値より6mm大きくなります。一般的な単行本は四六判もしくはA5判になります。

製本について
一般的な書籍の造りは、大きく上製本(ハードカバー)と「並製本(ソフトカバー)」の二種類に分けられます。
上製本とは
ボール紙を芯にして厚紙を巻いた、堅牢な造りの本です。布張りや革張りを施した豪華な造りにもできます。
中身を保護するため表紙が本文より一回り大きく花布(はなぎれ)や「スピン」など、本の耐久性や見た目、利便性を
高めるための加工が施されています。
上製本はさらに、背の形状によって「丸背」「角背」などに分けられます。
並製本とは
一枚の厚紙を表紙に用いた、軽快な造りの本です。表紙と本文用紙の大きさが揃っているのが一般的で、基本的な紙を
採用し、ページ数が同じ場合、並製本の方が費用を抑えることができます。
用語について
「編集なし」とは
著者の原稿を手直しせず組版のみ行い流通します。校正は1回のみとなります。
「簡易編集」とは
組版後、誤字脱字のみをチェックし、校正は1回のみとなります。
「通常編集」とは
原稿整理(文章および使用素材の取捨選択・リライトを含む)、構成の見直し、誤字脱字チェック、字句統一を行います。出力紙での校正は基本2回となります。
「編集済み完全データ」とは
インデザイン等の編集ソフトで作業が完成しており、印刷所に渡せる状態のデータ。校正は1回のみとなります。
「既刊本」とは
昔作った書籍を電子出版にする場合をさします。校正は1回のみとなります。
「文字データあり」とは
原稿がワード、一太郎等の文書作成ソフトでつくられたデータの場合をさします。
「手書き」とは
原稿が原稿用紙、ノート等に手書きで書かれている場合や印刷物の場合をいいます。